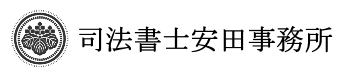商業登記
商業登記とは、会社や商人について取引上重要な一定の事項(商号、本店、資本金や役員等)を法務局に備えられた登記簿に記載して公開する制度です。主に会社を設立するときや、取締役等の役員の変更、合併などの組織の変更、新株の発行、会社の解散などの場合に登記を行います。
株式会社・合同会社(LLC)の設立登記
会社は「設立登記」をすることによって初めて、「法人」として成立します。
会社とは、企業形態のひとつで、営利を目的として活動する組織を指します。
会社は法律の規定によって「人格」を与えられた「人(法人)」の一種であり、生身の人間のように、権利を取得し、義務を負担すること(例えば、会社名義で原材料や物品を仕入れたり、商品を販売したり、運転資金の借入れをしたり、事務所・工場用の不動産を購入・賃借したり…)ができますが、私たち生身の人間のように形をもった存在ではないため、素性が知れず、取引の相手方などに不測の損害をもたらす恐れがあります。
よって、取引の安全を図るためにも、会社の名称(商号)・本店の所在・事業内容(目的)・役員といった取引上重要な事項を誰でも簡単に知ることができるよう、登記をして公示することが求められるのです。
会社はこの登記(設立登記)をすることによって初めて、法律上の人格を取得し、「法人」として認められることとなり、逆に登記をしていないと、会社名義での不動産の取得、原材料や物品の仕入れ、商品販売、運転資金の借入れもすべてできません。
設立手続きを、自分ですべて行うか、または司法書士・行政書士のような専門家に任せるか、お悩みの方もいらっしゃると思います。
費用・労力の面等から以下のような違いがでてきますので、ご検討ください。
【費用面(株式会社の場合)】
1.定款の印紙代
定款には「紙の定款」と「電子定款」の2種類があります。「紙の定款」を作成し、これに認証を受ける場合には、定款に4万円の収入印紙を貼らなくてはならないことになっています。一方、「電子定款」にはこのような決まりはありません。
しかし、この「電子定款」を作成するためには、特別なソフトや機器を備える必要があり、これに4万円以上の費用がかかります。
更に、法務省オンライン申請システムへの登録などの作業もあり、かなりの労力が必要となります。
当事務所では、この「電子定款」を作成し、認証を受けるための設備が整っているため、定款の印紙代はかかりません。
| 紙の定款 | 電子定款 | |
|---|---|---|
収入印紙代 |
4万円 | 0円 |
※別途、「紙の定款」・「電子定款」ともに、定款認証の手数料・定款の謄本の請求手数料がかかってまいります。
2.司法書士の報酬
司法書士の手数料、日当、交通費などです。当事務所では、会社プランによって金額が異なってまいりますので、一度ご相談ください。
【時間・労力面】
自分で会社を設立しようと思った場合、まずはご自身で本やインターネットで資料を集め、法律や手続きについて勉強することになると思います。
そして、定款や申請書などの書類を作成し、公証役場や法務局に何度も足を運び、質問や補正を繰り返すことになると思います。これには膨大や時間と労力が必要となります。このように細かく面倒な作業に手を煩わせるよりも、上手に私たちのような専門家を活用すれば、お客様は本業に全精力をつぎ込むことが可能となります。
当事務所では、お客様のご要望を伺い、その内容を精査したうえで、変更が必要な点についても法的な観点から適切なアドバイスをさせていただきます。
また、登記に必要な各種書面の作成はもとより、会社の根本規則である定款の文案作成・公証役場での認証手続きなど、会社設立に伴う諸手続きも一括してお手伝いさせていただきます。
【会社設立後のサポート】
会社を設立し、事業を展開していきますと、「税金」のことや「法律」のことなど、様々な問題にぶつかると思います。
しかしご安心ください。当事務所では、中小企業の皆さまが安心して事業に専念できるよう、様々な角度からサポートさせていただいております。
実際に法務部門を担当する職員を雇うとなると人件費が大きな負担となりますが、これらの事務をアウトソーシングすることによって、大幅にコストを削減できます。
具体的には以下のサービスを行っておりますので、会社設立後もぜひ当事務所をご活用ください。
- 登記の申請
- 許認可の申請
- 定款・議事録・契約書等の作成
- 売掛金の回収サポート
- 提携する税理士・弁護士・行政書士・社労士のご紹介
- ホームページ作成会社のご紹介
- 不動産の購入・売却のサポート(提携不動産業者のご紹介)
.png)
商号変更登記
会社の商号(登記簿に記載された会社名)を変更する場合、株主総会において定款の一部(商号に関する規定)を変更する旨の承認決議が必要となります。また、会社の商号は登記をして公示する必要があるため、その変更があった日から2週間以内に登記をしなければなりません。
【商号選定の制約】
商号は、原則として自由に決めることができますが、登記簿に文字として記載するうえで一定のルールがあります。
- 1.会社の種類に従い、商号中に「株式会社」「有限会社」「合同会社」「合資会社」「合名会社」という名称を用いなければならない。
- 2.「アラビア文字」「ハングル文字」「中国の簡体字」「※や()などの記号」は使用できない。
- 3.本店所在地が同一の他の会社と同じ商号は登記できません。
- 4.不正目的をもって、他の会社と誤認されるおそれのある商号を使用してはならないとされています。
一般的に、生身の人間の場合は「住所」と「氏名」をもって他者と識別をしますが、会社の場合は「本店」と「商号」をもって他社と区別することになります。
よって、「本店」と「商号」が全く同じ会社が存在するのでは、両社を識別することができなくなってしまうからです。
また、世間で広く認知されている会社の商号と同一または類似した商号を使用すると、差し止めや損害賠償を請求される可能性もあります。
当事務所では、登記に必要な各種書面の作成はもとより、類似商号の調査・議事録の作成など、一括してお手伝いをさせていただきますので、ぜひお気軽にご相談ください。
目的変更登記
事業の拡大・縮小に伴い、事業目的を追加・削除する場合、株主総会において定款の一部(目的に関する規定)を変更する旨の承認決議が必要になります。
会社の事業目的は、登記をして公示する必要があるため、その変更があった場合には変更登記をしなければなりません。
【目的選定の制約】
会社の事業目的については、会社法の施行に伴い、必ずしも具体的な事業目的を掲げる必要がなくなりました。
ただし、「適法性」「営利性」「明確性」という審査基準がありますので、株主総会に諮る前に、多少の調査は必要になりますので、注意は必要です。
当事務所では、登記に必要な各種書面の作成はもとより、目的の「適法性」「営利性」「明確性」調査、議事録の作成など、一括してお手伝いさせていただきますので、ぜひお気軽にご相談ください。
本店移転登記
「本店移転登記」とは、会社の本店所在地を変更する登記手続きのことです。
なお、本店所在地は、会社の定款の記載事項にもなっています。そのため、本店移転の際には、定款も忘れずに変更しなければなりません。
定款変更の際には、株主総会の決議が必要となりますから、手続きがより複雑になります。
ただし、定款では、本店は最小行政区画までの記載でも構わないことになっているので、定款を変更しなくてよいケースもあります。例えば、定款で「当会社の本店は、愛知県名古屋市に置く」と規定している会社が、名古屋市内で本店を移転する場合は、定款変更は不要です。
<定款記載の本店の所在地内での本店移転の場合>
| 定款に本店の所在場所まで記載 | 定款に本店の所在地までの記載 | |
|---|---|---|
| 株主総会の決議の要否 | 必要 | 不要 |
1.本店移転の登記をしないとどうなるの?
会社が本店の住所を移転したにもかかわらず、本店移転登記の手続きをしていなかった場合、登記簿の記載が実態とは異なることになります。会社の登記は一般の人に会社の実態を知らせるために行うものですから、本店移転が登記簿に反映されていないと不都合なことになります。
本店移転があった場合、本店移転登記をしなければならないことは、法律上も義務付けられています。本店移転登記には期限も設けられており、本店を移転した日から2週間以内に法務局で登記手続きをする必要があります。
もし、本店移転登記をせずに放置していれば、「登記懈怠」として会社の代表者が100万円以下の過料(罰金)を払わされることになります。
ただし、2週間の期限を過ぎれば直ちに過料が発生するわけではありません。法務局では、期限後であっても通常どおり登記を受付してもらえます。長期間放置していればいるほど、過料を払わされる可能性が高くなるということです。
2.本店移転登記を自分で行うメリットとデメリット
【メリット】
- ①手続き費用が抑えられる
司法書士に支払う報酬が発生しないため、手続き費用を抑えることができます。
【デメリット】
- ①手間や時間がかかる
登記手続きの際にはルールに則って申請書を作成したり、添付書類を用意したりしなければならず、手間や時間がかかるため、本業に支障が出てしまうことがあります。
- ②法務局に何度も行かなければならない
自分で手続きをする場合、登記申請時と登記完了時の少なくとも2回は法務局に出向く必要があります。更に、申請書類に不備があればやり直しが必要となり、法務局との間を何度も往復しなければならないこともあります。
- ③本店移転時に併せて注意すべき事項に気付きにくい
法務局で本店移転登記が受け付けられても、移転先の近くに似たような名前の会社があれば、営業ができないことがあります。また、自宅を本店にしている場合、代表取締役の住所変更登記が必要になることもあります。自分で手続きをすれば、こうしたことに気付きにくくなってしまいます。
3.本店移転登記を司法書士に依頼するメリットとデメリット
【メリット】
- ①面倒な手続きをすべて任せられる
登記を司法書士に依頼すれば、登記申請書の作成や添付書類の収集は司法書士にすべて任せられます。登記申請は司法書士が行いますので、自分で法務局に行く必要もありません。手続きのために時間を取られることもなく、本来の業務に集中することができます。
- ②株主総会議事録や取締役会議事録を作成してもらえる
会社の本店を移転するときには、定款変更が必要になることがあります。その場合には株主総会を開催して決議を行い、株主総会議事録を作成しなければなりません。また、取締役会の決議により本店所在地を決める場合には、取締役会議事録の作成も必要です。司法書士に本店移転登記手続きをご依頼いただいた場合には、株主総会議事録や取締役会議事録の作成もお手伝いいたします。
- ③定款を紛失した場合でも対応してもらえる
会社設立時の定款を紛失してしまい、定款の記載がどうなっていたかが分からないケースもあると思います。設立登記を行った法務局に登記申請書の閲覧申請を
したり、定款認証を行った公証役場で定款の謄本を請求したりすることで、定款が復元できる場合があります。司法書士は、定款の復元や再作成にも対応が可能です。
- ④法務局での本店移転登記申請を任せることができる
司法書士は法務局での本店移転登記申請の代理人になることができますので、ご依頼いただくことで、本店移転にかかる手間を大きく削減できます。支店がある場合など複雑なケースでも、ご自分で法務局に問い合わせをする必要がなくなり、スムーズに手続きを進めることができます。
- ⑤遠方の法務局への申請も任せられる
本店移転登記は、旧本店所在地の法務局に申請する必要がありますが、遠方に本店を移した場合には、旧本店所在地の法務局まですぐに行けないこともあります。郵送での申請も可能ですが、時間がかかるうえに、登記申請書や添付書類に不備があれば手続きが止まってしまうこともあります。司法書士はオンライン申請にも対応していますので、遠方の法務局への登記申請も迅速に行うことができます。
- ⑥移転先での商号調査もしてもらえる
移転先の近くに同じような名称の会社がある場合、登記は受け付けてもらえても、不正競争防止法違反となってしまい、営業ができなくなる可能性があります。司
法書士に手続きを依頼した場合には、商号調査も併せて行いますので、安心して本店移転ができます。
- ⑦会社所有の不動産の住所変更も依頼できる
会社所有の不動産がある場合には、本店移転により、不動産の所有権登記名義人住所変更登記も行う必要がでてきます。司法書士は不動産登記申請にも対応ができますので、法務局での手続きをまとめてお任せいただけます。
- ⑧本店移転に伴い必要となる手続き全般をサポートしてもらえる
当事務所は、税理士や社労士など他の専門家とも連携しております。税務署や年金事務所等での届出全般について専門家のアドバイスを受けられるため、手続きの不安がなくなります。
- ⑨役員変更登記を忘れることがなくなる
会社では、原則として2年に1回役員変更登記をする必要があり、変更登記を怠っていれば罰則もあります。司法書士に継続的なサポートをご依頼いただくことで、役員変更のタイミングも忘れることがなくなり、安心して会社経営に専念していただけます。
【デメリット】
- ①手続き費用がかかる
司法書士に支払う報酬が発生するため、手続きに要する費用が増えます。
| 司法書士に依頼する場合 | 自分で登記を行う場合 | |
|---|---|---|
|
メリット |
〇 面倒な手続きをすべて任せられる |
〇 手続き費用が抑えられる |
|
デメリット |
× 手続き費用がかかる |
× 手間や時間がかかる |
支店設置・移転・廃止登記
会社は、1か所ないし数か所の営業所を設けた場合、このうちの1つを主たる営業所(本店)とし、それ以外の営業所を「支店」とします。
会社の支店は、登記をして公示する必要があるため、支店の設置・移転・廃止などの変更があった場合には、その登記をしなければなりません。
当事務所では、登記に必要な各種書面の作成はもとより、議事録の作成など一括してお手伝いさせていただきますので、ぜひお気軽にご相談ください。
役員変更登記
会社の役員とは、取締役・代表取締役・監査役等を指します。役員に変更(就任、再任、辞任、解任、死亡等)があったり、またはその氏名や住所に変更があった場合には、役員変更の登記が必要になります。
また、既存の役員の任期がすでに満了しているような場合も、役員変更の手続きが必要となりますので、ご注意ください。
現行の会社法では、一定の条件のもと、取締役会や監査役を置くかどうかは任意となりました。会社の実情に合わせた機関設計が可能です。この場合、定款を変更したうえで、取締役会や監査役を廃止する登記や役員変更登記が必要です。
- 1.取締役の任期
原則として、選任後2年以内に終了する事業年度のうち、最終のものに関する定時株主総会の終結の時まで。
- 2.監査役の任期
原則として、選任後4年以内に終了する事業年度のうち、最終のものに関する定時株主総会の終結の時まで。
※非公開会社(株式の譲渡の際に会社の承認が必要な株式会社)においては、取締役・監査役共に、定款によって「選任後10年以内に終了する事業年度のうち、最終のものに関する定時株主総会の終結の時まで」と任期を伸長することができます。
| 任 期 | 取締役 | 監査役 |
|---|---|---|
原 則 |
2年 ※ | 4年 ※ |
|
例 外 |
10年 ※ | 10年 ※ |
※選任後上記期間内に終了する事業年度のうち、最終のものに関する定時株主総会の終結の時まで
当事務所に登記手続きをご依頼いただくお客様の中には、役員の任期満了に伴う変更登記を放置されているケースが多くみられます。役員の任期が満了した場合には、たとえ同じ人が続投する場合であっても、再度登記手続きをする必要があります。
また、会社の登記手続きには、登記期間の定めがあります。この期間を経過して登記手続きを放置しておりますと、過料(行政罰、罰金のようなもの)の対象となる場合があります。
当事務所では、登記に必要な各種書面の作成はもとより、ご希望があれば役員の方々の任期の管理、改選時期のお知らせ、各種議事録の作成など、末永くサポートさせていただきます。ぜひお気軽にご相談ください。
資本金変更登記

資本金は、会社の責任財産を裏付けるものですので、これを減少(減資)する場合には、会社債権者に対して公告や催告が必要となります。
また、会社の登記手続きには、登記期間の定めがあります。この期間を経過して登記手続きを放置しておりますと、過料(行政罰、罰金のようなもの)の対象となる場合があります。
当事務所では、登記に必要な各種書面の作成はもとより、会社債権者に対しての公告や催告手続きなど、資本金変更(増資・減資)に必要となる手続きを一括してお手伝いさせていただきますので、ぜひお気軽にご相談ください。
有限会社から株式会社への変更登記
1.特例有限会社から株式会社への変更登記
平成18年5月1日の「会社法」施行とともに「有限会社」という会社形態は廃止され、新たに「有限会社」を設立するということはできなくなりました。会社法施行時にすでに存在していた「有限会社」は、「特例有限会社」として存続することになります。
「特例有限会社」は、法律的には株式会社として扱われますが、「会社法の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律」の定める特例の適用により、従前の「有限会社」に類似した制度の適用を受けることになります。
「特例有限会社」はそのまま「特例有限会社」として存続することもできますし、一定の手続きを経て通常の「株式会社」に移行することもできます。ただし、通常の「株式会社」となった場合、当然に特例の対象からは除外されることになります。また、一度移行してしまうと、再び「特例有限会社」に戻すことはできませんので、手続きの際には、どちらの形態が今後の会社運営に適しているか熟考が必要です。
「特例有限会社」が特例適用のない通常の「株式会社」となるには、商号中の「有限会社」の文字を「株式会社」に変更したり、役員の任期に関する規定を設けたりと、定款の全体的な変更が必要となります。
当事務所では、登記に必要な各種書面の作成はもとより、新定款の文案や議事録の作成など、株式会社の移行に伴う諸手続きも一括してお手伝いさせていただきますので、ぜひお気軽にご相談ください。

2.特例有限会社から株式会社に移行するメリット・デメリット
【メリット】
- ①有限会社より相対的に信用力が増す
以前は株式会社が1000万円以上、有限会社が300万円以上といった最低資本金制度がありました(現在は廃止されています)ので、有限会社より株式会社の方が資本金の面で信用性が高いとされていました。
ただし、会社の信用は、創業年数が長い、財務状況の健全性、代表者個人の人柄など様々な要因により得られるものであり、現在は株式会社でも1円から設立することができることから、有限会社を株式会社に移行したとしてもそれだけで会社の信用が大きく増すことはないでしょう。
- ②合併、会社分割等の組織再編行為が行える
特例有限会社は吸収合併存続会社、吸収分割承継会社になることができません。
ただし、特例有限会社が吸収される会社合併(吸収合併消滅会社)、特例有限会社がその事業の全部又は一部を分割し他の会社に承継させる会社分割(分割会社)は行うことができます。
【デメリット】
- ①決算公告が義務付けられる
株式会社は貸借対照表等の決算書を、定款で定める公告方法により公告しなければなりません。官報公告ですと、最低6万円程度の費用がかかります。
- ②取締役等の役員改選時に登記手続きが必要となる
特例有限会社は任期の期限がないのに対し、通常の株式会社ですと取締役の任期は2年(非公開会社であれば最長10年まで伸長することができます)で、同一人を再選する場合でも取締役の変更登記が必要となります。
特例有限会社から株式会社への移行 |
|
| メリット |
〇 有限会社に比べて信用力が増す 〇 合併等の組織再編行為が行える |
| デメリット |
× 決算公告が義務付けられる × 取締役等の役員改選時に登記手続きが必要となる |
合併登記
業務提携やグループ再編などの目的で、会社の合併を考えることは多いと思います。新会社法の施行により、会社の合併制度は従前に比べて利用しやすくなりました。会社合併に興味がある方も多いのではないでしょうか。
1.会社の合併には2種類ある
複数の会社を1つの会社にすることを会社合併といいます。
会社法では、「会社は、他の会社と合併することができる。この場合においては、合併をする会社は、合併契約を締結しなければならない」(会社法第748条)と定められており、会社同士は合併契約により合併できるものとされています。
会社の合併には、「吸収合併」と「新設合併」という2つの方法があります。それぞれの違いは次のようになっています。
①吸収合併
一方の会社が、他方の会社を吸収する形の合併です。吸収する側の会社を存続会社、吸収される側の会社を消滅会社といいます。吸収合併では、消滅会社の持っていた権利や義務はすべて存続会社に承継され、消滅会社は解散することになります。吸収合併では、消滅会社の株式は消滅することになるため、消滅会社の株主は、株式の対価として、存続会社の株式・社債・現金等を受け取ることができます。

②新設合併
複数の会社が合併して新しい会社を設立する形の合併です。
新設合併で新しく設立される会社は新設会社と呼ばれ、元々あった会社はすべて消滅会社となります。新設合併では、合併する前の会社の持っていた権利や義務はすべて新設会社に承継され、消滅会社は解散します。
新設合併でも、吸収合併と同様、消滅会社の株式は消滅します。ただし、新設合併における消滅会社の株主が株式の対価として受け取れるのは、新設会社が発行する株式または社債等に限られます。吸収合併の場合のように、株主が現金を受け取ることはできません。これは、新設合併の場合に現金での清算を可能にすると、株主がいなくなってしまう可能性があるからです。

解散登記・清算登記
会社を消滅させたいけれど、どうすればよいのかわからないという方も多いのではないでしょうか。会社を消滅させるためには、法律で定められた手順に従って手続きを進めなければなりません。
まずは会社解散の手続きを行った後、会社の債権債務や財産を清算したうえで残余財産が残れば株主に分配し、最終的に清算結了の登記をする必要があります。
この一連の手続きをこなすには、法的・税務的な知識が必要となりますし、ただでさえ時間がかかる作業となりますので、自社だけで対処するのは非常に困難と思われます。
手間のかかる会社解散・清算手続き代行を当事務所にお任せいただくことで、スムーズに会社を消滅させることが可能となります。
「どこまでやってくれるの?」「費用はどのくらい?」等、まずはお気軽にお問合せください。

1.会社解散とは
会社の解散とは、これまでの会社の通常業務(営業活動)を停止して、会社を消滅させるための清算手続きに入ることを意味します。
会社を解散させるためには、株主総会を開いて解散する旨の決議をするところから始めなければなりません。この解散の決議は、特別決議(議決権の過半数を有する株主が出席し、出席した株主の議決権の3分の2以上が賛成する決議)で行う必要があります。
また、解散決議を行う際には、原則として解散後の清算の職務を行う「清算人」の選任も必要になります。解散すると、会社経営のために選任された取締役は当然に退任し、この清算人が解散後の清算事務を行い、また、会社を代表することになります。
なお、会社の解散は登記しなければなりませんので、解散の日から2週間以内に法務局で解散登記と清算人選任登記を行います。
会社を解散した後は、すぐに法人格が消滅するわけではなく、会社は清算の目的の範囲内で存続することになります。

2.清算手続きとは
株主総会で解散の決議をすれば会社を解散することはできますが、会社に残っている財産や債権・債務をそのままにして法人格を消滅させることはできません。会社を消滅させる前に、会社の財産状況を調査し、債権や債務を整理する必要があります。この一連の手続きを会社の清算手続きといいます。

その後、②清算人は2ヶ月以上の期間を定めて、債権を申し出る旨の官報公告と債権者への個別の催告を行います。
また、③債務の弁済や債権の取り立てを行い、不動産等の現金以外の会社資産は売却するなどして現金化します。
最後に、④残余財産が確定すれば、株主に残余財産を分配します。
一連の清算手続きが終わったら、⑤清算人は決算報告書を作成し、株主総会の承認を得る必要があります。
3.清算結了とは
清算結了とは、会社の財産や債権・債務がゼロになり、清算手続きが完了することをいいます。清算事務終了後、株主総会で決算報告書の承認を受けることにより、会社は清算結了となります。清算結了により、会社の法人格も消滅することになります。
ただし、手続きとしては法務局での清算結了登記を行って初めて、会社が完全に消滅したといえる状態になります。
清算結了の登記は、株主総会で決算報告書の承認を受けた日から2週間以内に法務局に申請する必要があります。なお、会社法の規定により、清算手続きで債権申出の公告や催告を行うのに、少なくとも2ヶ月はかかることになります。そのため、清算結了の日が、清算人選任後2ヶ月以内になっていれば、清算結了登記を受け付けてもらえませんので注意する必要があります。
4.解散・清算結了の必要性
会社が存在すれば、たとえ実際には営業活動をしていなかったとしても、法人住民税の均等割(最低7万円)が発生します。
また、休眠中とはいえど、役員の任期が満了すれば登記をする必要があり、これを怠ると過料(罰金)が科されることもあります。
また、会社が存続している限り、税務署への決算申告も通常どおり行わなければなりません。
このような出費をしないためには、原則として会社を解散し、清算結了する必要があります。これにより、会社は法律上消滅することになります。
5.休眠会社のみなし解散
休眠会社とは、最後に登記された日から12年を経過した株式会社のことをいいます。
つまり、長期間にわたって何も登記がされていない株式会社のことを、実態上稼働していない会社という意味で「休眠会社」と呼んでいるわけです。平成27年度以降、法務省は毎年休眠会社の整理作業を実施しています。
休眠会社の整理作業では、法務大臣が官報によって休眠会社に該当する株式会社に、2ヶ月以内に「事業を廃止していない旨の届出」をするよう公告します。当該株式会社が、この届出または役員変更等の登記をしない場合には、2ヶ月の期間満了の時に解散したものとみなされ、登記官の職権で解散登記がなされます。
みなし解散の通知が届いた場合、事業を継続するのであれば速やかに「事業を廃止していない旨の届出」を法務局に提出しなければなりません。届出の手続きは、通知書に必要事項を記載して法務局へ持参または郵送することにより完了します。
みなし解散の登記がされた場合には、登記後3年以内に限り、株主総会の特別決議により会社の継続が可能です。なお、会社を継続したときには、2週間以内に会社継続の登記申請をする必要があります。