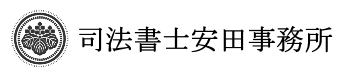�����E��������
�y�����ɂ��āz
�����o�L�Ƃ́H
�����o�L�Ƃ́A�s���Y�i�y�n�A�Ɖ��A�}���V�������j�𑊑������ۂɍs�����`�ύX�葱���̂��Ƃł��B�����ɂ��s���Y�̖��`�ύX�i�����o�L�j�́A�����������ł��͂����Ă���܂��B
���̑����o�L�̎葱���́u�@���ǁv�Ƃ��������ōs���܂��B�@���ǂ́A�s���Y�̏��ݒn�ɂ���ĊNJ���������Ă��܂��̂ŁA�Ⴆ�A����n��ɕs���Y����������ꍇ�ɂ́A���̕������NJ�����@���ǂ݂̂Ŏ葱��������Α���܂��B�������A�����̕s���Y���ʂ̎s�撬���ɂ܂������Ă���悤�ȏꍇ�ɂ́A���ꂼ��̕������NJ�����@���ǂ��Ⴄ�Ƃ������Ƃ����蓾�܂��B���̏ꍇ�ɂ́A���ꂼ��̖@���ǂ��ƂɎ葱�������Ȃ���Ȃ�܂���B�o�L�̐\���́A�l���@���ǂ֍s���Ē��ڎ葱�������邱�Ƃ��ł��܂����A�@���ǂ͂����܂Ő\�����ނ��t��������ł��̂ŁA���ލ쐬�̃T�|�[�g�܂ŏ\���ɑΉ����Ă���Ȃ��P�[�X������܂��B

�����o�L�̎葱���́A�K�v���ނ��������߂������W�߂邾���ł���ςȘJ�͂Ǝ��Ԃ�v���܂��B�܂��A������x�m�����Ȃ��Ə��ނ̍쐬�Ɍ˘f�����Ƃ������A�����Ɩʓ|�Ȃ��̂ł��B
���������ɂ��˗�����������A�s���Y�⑊���W�̒����A�K�v���ނ̎擾�E�쐬�y�ё����o�L�̐\���܂Ŗʓ|�Ȏ葱����S�čs���܂��B
�����o�L�ɂ͂��܂łɂ��Ȃ���Ȃ�Ȃ��Ƃ��������͂���܂���B
�������A
�����o�L�̎葱���������ɂ��̂܂ܕ��u���Ă����ƁA�ȉ��̂Ƃ���l�X�ȕs�s����������ꍇ������܂��B
- �����o�L�ɕK�v�ȏ��Г��{��Z���[�̏��[�Ȃǂ́A�����̕ۑ����Ԃ��߂���Ə�������邽�߁A�o�L�ɕK�v�ȏ��ނ������ɂ����Ȃ�B
- �����l�����S���Ă���ɑ������������A�����葱���Ɋւ��l����������B�S��������킹�����Ƃ��Ȃ��e���Ƒ����葱����i�߂Ȃ���Ȃ�Ȃ��Ȃ�A�b���������X���[�Y�ɂł��Ȃ��Ȃ�B
- �s���Y�p�������Ȃ��Ă��A�����ɔ��p���ł��Ȃ��B
- �s���Y��S�ۂɋ��Z�@�ւ��炨������悤�Ǝv���Ă��A�����Ɏ�邱�Ƃ��ł��Ȃ��B
- ���̑����l������ɖ@�葊�����œo�L�����A�����̎������������Ă��܂������ꂪ����B


���̂悤�ɁA�����o�L�͔푊���l�̎��S��ł��邾�����₩�ɑΉ����邱�Ƃ����߂��܂��B������O���瑊���o�L�����ꂸ�ɕ��u����Ă���P�[�X�͂悭����܂����A���������o�L������ƂȂ�ƁA�K�v���ނ��W�߂ēo�L����������܂łɐ���������P�N�ȏォ�����Ă��܂��P�[�X������܂��B�@
�u�s���Y�������Ƃ��đ�������̂��v�u���p���Ă�������̂��v�u�����l��N�ɂ���̂��v���A�������ׂ������͏��Ȃ��Ȃ��ł����A���߂Ɍ��߂đ����o�L�����邱�ƂŁA�O�q�������X�N��������邱�Ƃ��ł��܂��B
���S���m���ɕs���Y�̖��`�ύX���ς܂��邽�߂ɂ��A�����o�L�͐��Ƃł��铖�������ɂ��܂������������B
�����o�L�̂R�̕��@
�����ɂ́A�傫�������ĂR�̃p�^�[��������܂��B
- �@�@�葊���ɂ��ꍇ
- �A��Y�������c�ɂ��ꍇ
- �B�⌾��������ꍇ
�ɉ����āA���ꂼ��̕��@�ɂ�葊���o�L�̎葱�����i�߂Ă�������ɂȂ�܂��B
�@�@�葊���ɂ�鑊���o�L
�u�@�葊���v�Ƃ́A���@�Œ�߂�ꂽ�@�葊�����ł̑����̕��@�ł��B�⌾�������݂��Ȃ������ꍇ�ɂ́A�@�葊�����ł̑����o�L���I������邱�Ƃ�����܂��B
�Ⴆ�A�@�葊���l����e�Ǝq���Q���̏ꍇ�ɂ́A����������e���P/�Q�A�q�������ꂼ��P/�S�ƂȂ�܂��B���̖@�葊���ŕs���Y�𑊑�����ꍇ�ɂ́A�@�葊�����Ɠ������L���������ɂ�薼�`�ύX���s�����ƂɂȂ�܂��B
�@�葊���ɂ�鑊���o�L�ł́A��Y�������c���s�v�ɂȂ�܂��̂ŁA�o�L�葱���̎�Ԃ����Ȃ��Ȃ�Ƃ��������b�g�͂���܂����A�����I�ɕs���Y�̋��L�ɔ����g���u�����������鋰������邱�Ƃ͗������Ă����Ȃ���Ȃ�܂���B
�s���Y�����L���`�̏ꍇ�́A���݂┄�p������ɂ����̑����l�̓��ӂ��Ȃ���Ύ葱����i�߂邱�Ƃ��ł��܂���B
���L�҂���Ɏ����Ɠ����l���ł���Ζ��Ȃ��̂ł����A�Ⴆ�A���L�҂ł���Z�킪�S���Ȃ����悤�ȏꍇ�A�����ɂ���ĖS���Ȃ����Z��̔z��҂�q�����V���ȋ��L�҂ɂȂ��Ă��܂����Ƃ��l�����܂��B�܂��A���L�҂������̎����𑼐l�ɏ��n���Ă��܂����Ƃ��l�����Ȃ��͂���܂���B
�����������ꍇ�ɂ́A��莩���Ƃ͊W���̔������L�҂�����邱�Ƃɂ���āA�s���Y�̏������ɂ��āA�X�Ɉӎv���ꂪ����Ȃ�܂��B
�@�葊���ɂ�鑊���o�L |
|
|
�����b�g |
�Z ��Y�������c���s�v |
|
�f�����b�g |
�~ �����I�ɕs���Y�̋��L�ɔ����g���u���̔����̋��� |
�@�葊�����ɂ�鑊���o�L�́A�����I�Ȃ��Ƃ��������đI������K�v������܂��B�@�葊����I������ꍇ���A���Ƃł���i�@���m�̃A�h�o�C�X���Ď葱����i�߂�̂��K�ȑΉ��ł��B
�A��Y�������c�ɂ�鑊���o�L
�u��Y�������c�v�Ƃ́A�@�葊���l���Q���ȏア��ꍇ�ɁA�����l�̑S������Y�̔z���Ȃǂɂ��Ď�茈�߂��s���b�������̂��Ƃ������܂��B��Y�������c�́A�����ȑ����̎����Ƌ��ɁA��ɑ����g���u�����������Ȃ��悤�ɂ��邱�Ƃ��ړI�ł��B���̂��߁A�����l�S���̎Q�����K�{�v���ŁA�P���ł��s�Q���̏ꍇ�ɂ͖����ƂȂ�܂��B��Y�������c�Ō��܂������e�́A�u��Y�������c���v�ɋL�ڂ��āA�����l�S���������E���i����j���܂��B��Y�������c�Ɋ�Â������o�L�́A���̈�Y�������c����Y�t���Đ\�����邱�ƂɂȂ�܂��B
�Ȃ��A�����l�̒��ɖ����N�҂�����ꍇ�ɂ́A�ƒ�ٔ����œ��ʑ㗝�l��I�C���Ă����Ȃ���Ȃ�Ȃ��P�[�X������܂��̂ŁA���ӂ��K�v�ł��B�܂��A�F�m�ǂ̕�������ꍇ�ɂ́A�ƒ�ٔ����Ő��N�㌩�l��I�C���Ă����Ȃ��Ă͂Ȃ�܂���B

�܂��A��Y�������c������ۂɂ́A�����l���u�C�O�ɏZ��ł���v�u�A�������Ȃ��v�Ȃǂ̎���ɂ��A���c�ł��Ȃ��Ƃ�����肪�������邱�Ƃ��悭����܂��B���̂悤�Ȗ��̂���P�[�X�ɂ����Ă��A�ł��邾���X���[�Y�Ɉ�Y�������c���i�ނ悤�i�@���m���T�|�[�g�������܂��B
�B�⌾���ɂ�鑊���o�L

�⌾���ł悭���p�������̂Ƃ��ẮA�����̎菑���ō쐬����u���M�؏��⌾�v�ƁA���ؖ���Ō��ؐl�Əؐl�Q���̗�����̂��ƍ쐬����u�����؏��⌾�v������܂��B
���M�؏��⌾�́A���@�Œ�߂��v�������Ă��Ȃ��ƈ⌾���̂������ɂȂ��ό��������̂ł��B�܂��A����Ŏ��M�̈⌾�������������Ƃ��Ă��A���̏�ŊJ�����Ă͂Ȃ炸�A�ƒ�ٔ����ɂ����āu���F�v�̎葱�������Ȃ���Ȃ�܂���̂Œ��ӂ��܂��傤�B
�����A�u�⌾����������Ȃ��v�A�u���M�؏��⌾�̎戵�����ǂ����������������Ȃ��v�ȂǁA�⌾���Ɋւ��ĕs���_������A���Ƃł���i�@���m�̃A�h�o�C�X�ɉ����đ����o�L�葱����i�߂܂��傤�B
�y���������ɂ��āz
���������Ƃ́A�푊���l�̍��Y���v���X�̍��Y�i�a���A�L���،��A�s���Y���j�A�}�C�i�X�̍��Y�i�؋����j���킸�S�Ď����������p�����Ƃ����ۂ���ӎv�\���ŁA�u���������\�q���v�Ƃ������ʂ��ƒ�ٔ����ɒ�o���čs���܂��B
�����������F�߂���ƁA���������������҂́A���̑����Ɋւ��Ă͏��߂��瑊���l�łȂ��������̂Ƃ݂Ȃ���A���������������҂̎q�⑷���������邱�Ƃ�����܂���B
�������������邱�Ƃ̂ł������
���@�ł́u���Ȃ̂��߂ɑ����̊J�n�����������Ƃ�m����������O�ӌ��ȓ��Ɂv�������������Ȃ���Ȃ�Ȃ��ƋK�肳��Ă��܂��B���̎O�ӌ��̊��Ԃ��u�n�����ԁv�Ƃ����܂��B
���̏n�����Ԃ���̓I�ɂ��J�n����̂��ɂ��ẮA�Ⴆ�A�����l���푊���l�̎��S�͒m���Ă��邪�A�������Y�͑S���Ȃ����낤�ƐM���Ă����ꍇ�Ȃǂ́A�u���Ȃ̂��߂ɑ����̊J�n�����������Ƃ�m�������v�ɂ͊Y�����Ȃ��Ƃ���Ă��܂��B
�܂��A���Y�������v���X���}�C�i�X���̔��f������ꍇ��A���Y���S���e�n�ɓ_�݂��Ă���ꍇ�Ȃǂɂ͑S���Y�̒����Ɏ��Ԃ������邱�Ƃ��\�z�����̂ŁA���̏ꍇ�ɂ͗��Q�W�l����n�����Ԃ̐L�����ƒ�ٔ����ɐ������邱�Ƃ��ł��܂��B
�Ȃ��A�v�������������g�������l�ɂȂ��Ă����ꍇ�́A���̂��Ƃ�m����������n�����Ԃ��n�܂�܂��B�K�������푊���l�̎���m����������n�܂�Ƃ͌���܂���B

��������������ꍇ�̒��ӓ_
�P�D�������������邱�Ƃ��ł��Ȃ��Ȃ�ꍇ
��������������O�ɁA���Ƃ��������Y�̈ꕔ�ł����Ă��A�����i���p�����j�����Ă��܂��ƁA�S�Ă̍��Y�������p���ӎv�\���i�P�����F�j���������̂Ƃ݂Ȃ���A�������������邱�Ƃ��ł��Ȃ��Ȃ�܂��B
�������A�Ɖ��̉������C������ȂǍ��Y�̕ۑ���ړI�Ƃ���s�ׂ́u�����v�ɊY�����܂���B
�Q�D�v�������������������l�ɂȂ��Ă��܂��ꍇ
�����l�ƂȂ�҂́A�ȉ��̂Ƃ���@���ŏ��ʂ���߂��Ă��܂��B
���@��̑����̏����i�z��҂͏�ɑ����l�ƂȂ�܂��B�j
��P���ʁ@�q�i�{�q���܂ށj
��Q���ʁ@���n�����i�����c����ȂǏ�̐���j
������Ƒc���ꂪ����ꍇ�́A���e���̋߂����ꂾ���������l�ƂȂ�A�c����͑����l�ɂ͂Ȃ�܂���B
��R���ʁ@�Z��o��
��L�̂ق��A�푊���l�̎q��Z��o�����A�푊���l������Ɏ��S���Ă����ꍇ�A��P�����Ƃ����āA�푊���l�̑���Б��܂��͉���Â������l�ƂȂ�܂��B
�������揇�ʂ̎ґS�����A���������Ȃǂɂ�葊������L���Ȃ��Ȃ������́A�����ʂ̎҂������l�ƂȂ�܂��B���̏ꍇ�A�����ʎ҂��푊���l�̎؋��Ȃǂ������p�������Ȃ���A�����ʎ҂����������̎葱��������K�v������܂��B
�揇�ʎ҂��������������Ă��邩�ǂ����m�肽���ꍇ�́A�푊���l�̍Ō�̏Z���n���NJ�����ƒ�ٔ����ɏƉ�邱�Ƃ��ł��܂��B

�R�D���łɈ�Y�������c���I�����ꍇ
�푊���l�̍��Y�̒��Ɏ؋��Ȃǃ}�C�i�X�̍��Y������ꍇ�́A��Y�������c�̓��e�����҂Ɏ咣�ł��Ȃ��̂Œ��ӂ��K�v�ł��B
�Ⴆ�A�����l�̒��Ƀv���X�̍��Y����ؑ������Ȃ��҂�����ꍇ�ł��A�}�C�i�X�̍��Y�͖@�葊�����ɏ]���ē��R�Ɉ����p�����ƂɂȂ�܂��B
�܂��A����̑����l�������؋��������A���̑��̑����l�͈�؎؋���Ȃ��Ƃ�����茈�߂����Ă��A���҂̓��ӂ��Ȃ���A���҂ɑ��Ă͋��c�̓��e���咣�ł��܂���B����́A���҂̑��ň���I�ɍ��������p�������l���w��ł���Ƃ���ƁA���҂��s���v����\�������邩��ł��B���҂ɂƂ��Ă݂�A�N�����҂ɂȂ邩�ɂ���č�����ɉe�����łĂ��܂��̂œ��R�ł��B
�]���āA�u��Y�������c�Řb���������܂Ƃ܂���������v�I�v�Ƃ����킯�ł͂Ȃ��A�؋��Ȃǂ����p�������Ȃ��ꍇ�́A������������菳�F�̎葱�������邱�Ƃ��K�v�ɂȂ�܂��B���ꂩ���Y�������c��\�肵�Ă�������������A���̓_�ɂ͂����ӂ��������B